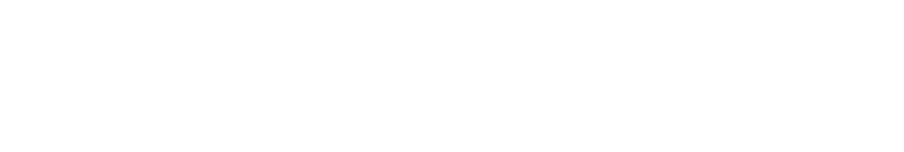- HOME>
- 糖尿病性神経障害
糖尿病性神経障害とは

糖尿病性神経障害とは、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症とともに「糖尿病の三大合併症」と呼ばれる疾患です。原因は糖尿病による高血糖状態が長期間続いた結果、神経周囲の血管が損傷したり、神経自体が変質してしまい、神経の働きが鈍くなったりすることです。
糖尿病性神経障害は大きく2種類に分けられます。1つは同時に複数の神経に障害が起きる多発神経障害。もう1つは1本の神経だけに障害が起きる単神経障害です。一般的には前者の多発神経障害が多く見られます。
糖尿病性神経障害の症状
糖尿病性神経障害の症状は主に末梢神経に現れます。末梢神経とは、体の末端の方まで伸びている神経のことで、手足の痛みなどの感覚を司る感覚神経、筋肉を動かす運動神経、心臓や胃腸の働き、排尿などをコントロールする自律神経を指します。
具体的には、以下のような症状が現れます。
外眼筋麻痺
糖尿病によって末梢神経が損傷し、眼のまわりの筋肉を制御する神経が弱くなり、目の動きが制御できなくなるため起こります。
顔面神経麻痺
糖尿病によって末梢神経が損傷し、顔面神経の神経支配が弱くなり、顔の筋肉の運動が制御できなくなるため起こります。
突発性難聴
糖尿病によって内耳の神経が損傷し、音を聞くための神経が弱くなるため、急激に聴力が低下します。
立ちくらみ
糖尿病によって自律神経が損傷することで血圧調節に不具合が生じるため、急激に立ち上がると血圧が下がり、立ちくらみが起きます。
不整脈
糖尿病によって自律神経が損傷し、心臓の動きを制御する神経が弱くなるため、心拍数が乱れたり、不規則なリズムで動いたりするようになります。
胃の蠕動(ぜんどう)障害
糖尿病によって自律神経が損傷し、胃の動きを制御する神経が弱くなるため、食事の消化や胃の排出が遅くなり、胃もたれや吐き気などが生じます。
下痢、便秘
糖尿病によって神経や筋肉が損傷し、腸の動きが遅くなったり、腸の働きに障害が出たりするため、排便に不具合が生じます。
排尿障害
糖尿病によって膀胱の神経や筋肉が損傷し、排尿の制御が上手くいかなくなり、頻尿や尿意が常にある状態になります。
勃起障害
糖尿病性神経障害は陰茎の神経にダメージを与え、陰茎への血流を制御する神経の働きを妨げることで勃起障害が起こります。
手の痺れ、疼痛、感覚麻痺
糖尿病性神経障害によって末梢神経が傷つくと、手足の末端から感覚神経が影響を受け、手の痺れ、疼痛、感覚麻痺が生じます。
筋萎縮
糖尿病性神経障害によって末梢神経が傷つくと、筋肉に必要な神経刺激が届かず、筋肉の萎縮が生じます。
こむらがえり
糖尿病性神経障害によって足の筋肉の神経が傷つくと、筋肉の収縮と弛緩が正しく調整されず、こむらがえりが起こりやすくなります。
皮膚の潰瘍(かいよう)
糖尿病性神経障害によって末梢神経が傷つくと、皮膚の感覚神経が影響を受け、皮膚の損傷が早く治らなくなり、潰瘍が生じることがあります。また、末梢神経障害によって、皮膚の乾燥や感覚の低下が起こり、皮膚の状態が悪化することがあります。
糖尿病性神経障害を放置していると…
糖尿病性神経障害の原因は糖尿病による高血糖状態であるため、治療をせずに放置していて改善するものではありません。
むしろ症状が進行すると、例えばしびれや痛みなどで夜眠れなかったり、足の関節や骨が変形したりすることもあります。足の感覚神経に障害が生じ、熱さや痛みを感じにくくなると、足にやけどや怪我を負っていても気づかず、重症化した結果、足の切断が必要になる場合もあります。立ちくらみが悪化して立つことができなくなることもあれば、大小便を失禁してしまう可能性もあります。
「もしかして」と思ったら
糖尿病性神経障害の予防、治療の基本は血糖値のコントロールです。上記のような症状がある場合は、横内内科 循環器・糖尿病内科を受診し、その指示にしたがってください。血糖値のコントロールには専門的な検査と知識が必要です。くれぐれも自己判断で対処しないようにしましょう。
また、糖尿病性神経障害の症状がない場合でも、健康診断などで糖尿病の傾向があると指摘された方は、早い段階で医師の診断を受けることをおすすめします。