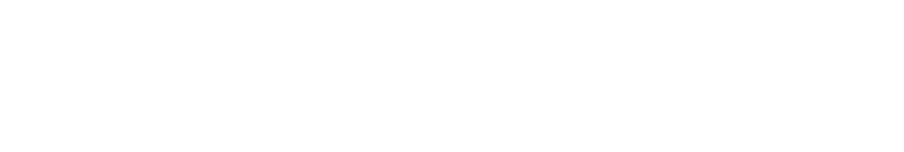- HOME>
- 妊娠糖尿病
妊娠糖尿病とは

糖尿病は糖代謝異常、つまり血液内の糖(血糖)をエネルギーとして上手く使えなくなる状態になる疾患です。妊娠糖尿病とは、妊娠中に初めて発見された糖代謝異常を指します。
そのため妊娠前からすでに糖尿病にかかっている場合、もしくは血糖値が妊娠糖尿病の基準よりも明らかに高く、糖尿病の基準を満たしている場合は、妊娠糖尿病とは診断されません(専門的には「妊娠中の明らかな糖尿病」と言います)。
妊娠中の明らかな糖尿病は、妊娠糖尿病に比べてより深刻な疾患です。そのため厳しい血糖値コントロールが必要になります。
なお、すでに糖尿病と診断されている場合、健康な赤ちゃんを産むためにも、糖尿病に詳しい病院できちんと検査を受けて自身の健康状態を把握したうえで、計画的に妊娠をするようにしましょう。
妊娠糖尿病の症状
母体が高血糖状態になると、へその緒で繋がっている赤ちゃんも高血糖状態になります。すると、母子ともに以下のような合併症にかかる可能性があります。
母体
- 帝王切開率の上昇
- 流産・早産
- 妊娠高血圧症候群
- 羊水量の異常
- 肩甲難産
- 網膜症・腎症
- 感染症の併発 など
赤ちゃん
- 形態異常
- 巨大児
- 心臓の肥大
- 低血糖
- 多血症
- 電解質異常
- 黄疸
- 新生児低血糖
- 胎児死亡 など
妊娠糖尿病になりやすい方
妊娠糖尿病になりやすい方の要因として、以下のようなものが挙げられます。
- 家族に糖尿病の方がいる
- 肥満
- 35歳以上の高年齢妊娠である
- 巨大児分娩の経験がある
- 原因不明の習慣流早産の経験がある
- 原因不明の周産期死亡の経験がある
- 先天奇形児の分娩歴がある
- 尿検査で「強い尿糖陽性」だと言われている
- 尿検査で2回以上尿糖陽性を指摘されたことがある
- 妊娠高血圧症候群
- 羊水過多症 など
妊娠糖尿病の検査は、妊娠をした方全員が受ける必要がありますが、上記の要因に当てはまる方は、特に積極的に検査を受けることをおすすめします。また、妊娠を予定している方は、事前に検査を受け、異常がないかを確かめておきましょう。
妊娠と糖代謝異常の関係性
妊娠と糖代謝異常には深い関係があります。なぜなら、妊娠をすると胎盤から分泌されるホルモンと酵素の影響で、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの働きが抑えられるとともに、インスリンそのものが破壊されてしまうからです。そのため、妊娠していない時と比べて糖代謝異常が起こりやすくなるため、血糖値が上がるのです。
妊娠糖尿病の診断方法
妊娠初期に血糖値を測定し、高かった場合はブドウ糖負荷試験という検査を行って診断します。この時に問題がなかった場合でも、妊娠が進むにつれてインスリンが効きにくくなるので、妊娠中期(24~28週)に再度検査を受ける必要があります。妊娠した方のうち、100人に7~9人は妊娠糖尿病と診断されます。「自分は大丈夫」と思わずに、きちんと検査を受けるようにしましょう。
産後も糖尿病の症状は続くのか?
妊娠糖尿病になると、食事療法を中心とした治療によって、血糖値を厳重に管理しなければなりません。場合によっては赤ちゃんに悪影響の出ないインスリン注射も必要になります。
しかし妊娠糖尿病にかかった方は多くの場合、産後に正常化します。そのため「産後もこの治療が続くのか」と悲観する必要がありません。産後6~12週間後に再び検査を受け、妊娠糖尿病が治っているかどうかを確認してもらいましょう。
ただし、一度妊娠糖尿病になった方は、妊娠糖尿病にかからなかった方と比べると、約7倍糖尿病になりやすいことがわかっています。そのため、定期的に検査を受け、自分の健康状態を知っておく必要があります。