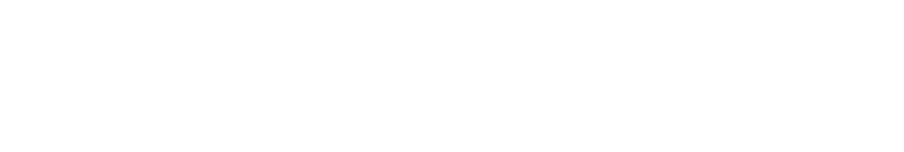- HOME>
- 高血圧の治療
高血圧症の治療方法

高血圧症の治療方法は大きく2つに分けられます。1つは食生活や運動などの生活習慣の見直し、もう1つは薬物療法です。
生活習慣の修正
食事療法
塩分を制限する
日本人の平均塩分摂取量は1日約10gですが、厚生労働省が推奨している食塩摂取量は、1日男性で7.5g未満、女性で6.5g未満となっています。すでに高血圧症が見られる場合は、1日6g未満を目標にします。
塩分摂取量を減らすために、食事の際は以下の点に注意します。
- 漬物・佃煮・干物・練り製品・肉加工品(ハムやソーセージ)などは控える
- 汁物や麺類は、1日1杯までとし、スープは飲まない
- 外食・市販弁当・惣菜は症状に応じて制限する
エネルギー摂取量の適正化
肥満は高血圧症の主な原因の1つです。肥満を解消するためには、エネルギー摂取量をエネルギー消費量よりも少なくする必要があります。そのために必要なのがエネルギー摂取量の適正化です。
高血圧症の治療においては、年齢・性別・身体活動量・肥満度・血糖コントロール・合併症などを考慮して、適正なエネルギー摂取量を設定します。
ミネラル分の積極的摂取
ミネラル分であるカリウムは塩分を尿中に排出し、体内の塩分濃度を正常化する働きがあります。カリウムは新鮮な野菜、海草、果物などに多く含まれているため、高血圧症の方や高血圧の傾向がある方は、積極的に摂取するようにします。
カリウムは果物にも多く含まれますが、果物には果糖が多く、食べ過ぎによる血糖値や中性脂肪値の上昇、肥満リスクの上昇が考えられるため、なるべく野菜、海藻から摂取することをおすすめします。
また、適量のカルシウムやマグネシウムには血圧を下げる作用があるとされています。カルシウムは低脂肪の乳製品、マグネシウムは胚芽米や胚芽パンなどから摂取できます。
摂取アルコール量の制限
過度のアルコール摂取は、高血圧の原因となることがわかっています。飲酒をする習慣がある場合は頻度を減らし、飲む量も適正量を心がけましょう。
日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン2019」は、1日の摂取アルコール量を男性で20~30g、女性で10~20g以下に抑えるよう推奨しています。
例えばアルコール度数5%のビールを500ml飲んだ時の摂取アルコール量が20g程度、350mlで14g程度です。日本酒で言えば1合が22g程度、12%のワインなら375mlで36gとなります。
運動療法
運動療法として効果のある運動とは、
- 定期的に、なるべく毎日
- 運動量は1回10分以上、1日30~40分以上(※)
- 強度は「ややきつい」と感じる程度
- 有酸素運動
※毎日運動の時間を確保できない場合は、1週間の総運動時間や総エネルギー消費量で計算しても構いません
とされています。運動そのものに血圧を下げる効果があるほか、肥満の解消にも効果が期待できます。
なおウォーキングや階段昇降、ジョギングやランニング以外にも、通勤など、日常生活の中で行う動作も効果的です。無理をせず、まずはできる範囲から始めることが大切です。
その他の生活習慣の改善
喫煙
たばこに含まれる化学物質は血管の収縮を促進するため、高血圧症の方や高血圧の傾向がある方は禁煙が必要となります。
ストレス
身体的、精神的ストレスを感じると、血圧が上昇することがわかっています。社会生活を営む以上ストレスは避けにくいものですが、ストレスを上手く発散する方法を見つけたり、睡眠や入浴、散歩など、体の緊張をほぐすような時間の過ごし方を探したりすることが大切です。
薬物療法
高血圧症に対して処方される薬には、様々な種類があります。それぞれの薬にメリット、デメリットがあり、患者様の状態に応じて単独で処方したり、組み合わせたりして処方します。以下ではその一部を紹介します。
カルシウム拮抗薬(血管拡張薬)
血管にはカルシウムが流入すると収縮する性質があるため、カルシウムの流入を防ぐことで血管を拡張し、血圧を下げます。飲み始めに顔のほてり、頭痛、動悸、便秘などの副作用が出る場合があります。血管拡張薬にはカルシウム拮抗薬以外にも様々な種類があります。
利尿剤
尿量を増加させ、血液量を減らすことで血圧を下げます。副作用としては、糖尿病の悪化、尿酸値の上昇、脱水症状の進行などが見られます。
神経遮断薬
心臓への余分な刺激を抑えて血管の緊張をとり、血圧を下げます。咳が出る、高カリウム血症に陥るといった副作用が出る場合があるほか、腎臓障害がある方の場合は腎動脈の狭窄が進むことがあります。