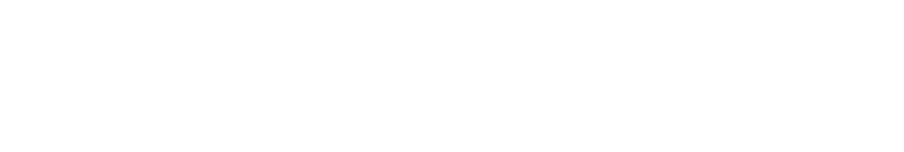- HOME>
- 糖尿病腎症
糖尿病性腎症とは
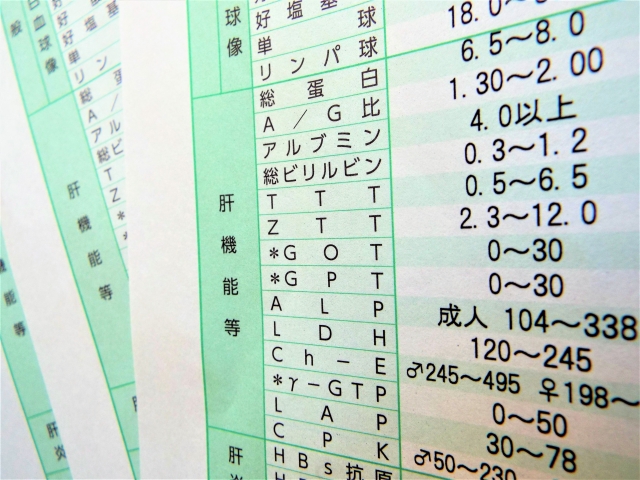
糖尿病性腎症とは、糖尿病性神経障害、糖尿病性網膜症とともに「糖尿病の三大合併症」と呼ばれる疾患の1つです。
腎臓は血液の中に含まれる老廃物を濾過し、尿として排泄することで、体内の水分量や血圧などを調節しています。糖尿病による高血糖状態が続くことで、腎臓の濾過装置である糸球体に張り巡らされている毛細血管が詰まったり、破れたりするのが糖尿病性腎症です。
根本的な原因はまだわかっていませんが、自覚症状がほとんどないにもかかわらず、重症化すると様々な症状や合併症が起こり、その方の生活に重大な悪影響を及ぼします。
糖尿病性腎症の症状
糖尿病性腎症の症状は、重症度に応じて第1期〜第5期に分類されています。以下ではそれぞれのステージにおける症状について説明します。
第1期・第2期
第1期・第2期はそれぞれ「腎症前期」「早期腎症」と呼ばれます。このステージでの症状はごく少量の蛋白尿です。蛋白尿とは、本来含まれないはずの尿蛋白(アルブミン)が尿中に見つかるようになる状態です。腎症が進行するにつれ、血圧の上昇やそれに伴う腎臓の毛細血管の損傷拡大が起こりますが、まだ自覚症状はありません。
第3期
早期腎症が進行すると、第3期「顕性腎症期」に入ります。腎臓の毛細血管の損傷とともに濾過機能がさらに低下し続けると、血液内に余分な水分や不純物が残りやすくなります。その結果として、全身のむくみやだるさ、貧血といった自覚症状が現れるようになります。
第4期・第5期
さらに症状が進行すると、第4期「腎不全期」、第5期「透析療法期」に入り、腎臓で尿を作り出すことができなくなります。しかし体内では老廃物が作られ続けるため、放っておくと体内に毒素や余計な水分が溜まり、心臓や肺、胃腸などが正常に働かなくなっていきます。この段階になると、機械を使って血液を浄化する「血液透析療法」が必要になります。
なお、2012年の調査によれば、全透析患者中、糖尿病性腎症が原因で透析を受けている方の割合は44.1%に上ります。
「もしかして」と思ったら
第1期・第2期では自覚症状がないものの、この段階で食事や運動を通じて血糖値をコントロールすれば、腎臓の濾過機能の低下を食い止め、症状を改善することが可能です。しかし第3期以降になると、症状の悪化を遅らせることはできても、改善することは難しくなります。
そのため、健康診断などで尿蛋白値(g/gCr)もしくはアルブミン値(mg/gCr)の異常が指摘された場合は、「何か症状が出ているわけでもないのだから、放っておいてもいいだろう」と思わず、できるだけ早く横内内科 循環器・糖尿病内科を受診するようにしてください。