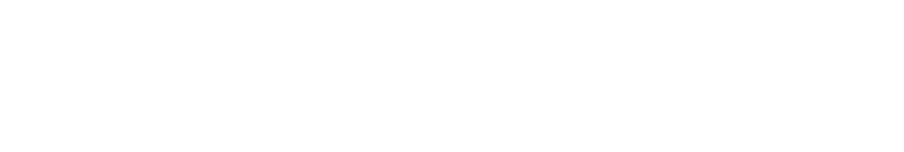- HOME>
- 蛋白尿
糖尿病と蛋白尿の関係性
蛋白尿とは
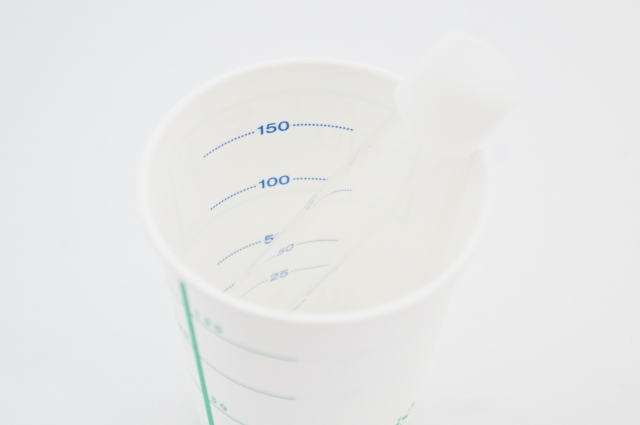
蛋白質は私たち人間の体の15~20%を占める栄養素です。筋肉、臓器、肌、髪、爪は蛋白質で構成されていますし、体内のホルモンや酵素、免疫物質なども蛋白質、体内で栄養素の運搬を担っているのも蛋白質です。
それほど重要な栄養素なので、蛋白質は通常体外に排出されることはなく、体内で使われます。しかし糖尿病が原因で腎臓に問題が発生すると、蛋白質が尿の中に混ざり込んでしまい、蛋白尿として排泄されてしまうのです。
なぜ糖尿病で蛋白尿が起きるのか
糖尿病が原因で蛋白尿が起きるのは、高血糖状態による腎臓機能の低下が原因です。
人間の体は、血液中の糖(血糖)を適正な量に保つために、膵臓からインスリンという血糖値を下げるホルモンを分泌しています。糖尿病は、長引く高血糖状態が原因でインスリンの分泌量減少や、血糖降下能(血糖値を下げる力)の低下、抵抗性(体の細胞のインスリンへの反応しにくさ)の上昇が起きる疾患です。
糖尿病が進行し、高血糖状態が慢性化すると、体中の毛細血管が傷み始めます。糖尿病は様々な合併症を引き起こしますが、これらの合併症は主に毛細血管の損傷が原因です。
腎臓は血液を濾過することで、体に必要な物質と不要な物質を分類する臓器です。この濾過を行うフィルターの役割を担っているのが、糸球体と呼ばれる部分です。糸球体は毛細血管の集まりです。そのため、糖尿病が進行すると高血糖が原因で損傷が起き、正常に機能しなくなります(「糖尿病性腎症」と呼びます)。
結果として、本来必要なはずの蛋白質を尿に混ぜ込んでしまい、蛋白尿として排泄してしまうのです。
その他の蛋白尿の原因
蛋白尿は糖尿病以外に、IgA腎症(慢性糸球体腎炎)、ネフローゼ症候群、血管炎などの免疫や遺伝の疾患、高血圧や肥満といった生活習慣病、そして起立性蛋白尿の場合にも見られます。
IgA腎症(慢性糸球体腎炎)
IgA腎症は、腎臓の糸球体で免疫グロブリンA(IgA)という蛋白が異常沈着を起こす疾患です。これは腎臓の炎症や障害を引き起こし、蛋白尿や血尿などの症状が現れます。
ネフローゼ症候群
ネフローゼ症候群は腎臓病変や免疫疾患が原因で腎臓に障害が生じる疾患です。主な症状として大量の蛋白尿が見られます。
血管炎
血管炎は、血管に炎症が生じる疾患で、腎臓にも影響を及ぼすことがあります。腎臓の糸球体に炎症が生じると、蛋白尿や血尿などの症状が現れることがあります。
高血圧
高血圧が長期間高い状態が続くことによって、腎臓に損傷を与えることがあります。その結果、腎臓の機能が低下すると、蛋白尿が現れる場合があります。
肥満
肥満状態が続くと腎臓に負担をかかるとともに、脂肪細胞から分泌される物質が腎臓に悪影響を与えるため、蛋白尿に繋がることがあります。
起立性蛋白尿
起立性蛋白尿とは、立ち上がったり運動したりすることで蛋白尿が現れる症状を指します。腎臓に病気がなくても腎臓の機能に影響を与えることがあるため、検査が必要です。
糖尿病による蛋白尿を放置すると…
糖尿病が原因の蛋白尿は糖尿病性腎症が進行しているサインです。そのため、何もせずに放置していると、症状はますます悪化し、最終的には腎臓がまったく機能しなくなり、透析治療や腎臓移植が必要になるリスクがあります。
また蛋白尿は心筋梗塞や脳梗塞といった、命に関わる疾患のリスク要因としても知られています。腎機能の低下によって血管内に老廃物が溜まることで、心臓や脳の血管が詰まってしまうのです。
初期の糖尿病性腎症には自覚症状がないため放置してしまいがちですが、健康診断などで蛋白尿が見つかったら、できるだけ早い段階で詳細な検査や治療を行う必要があります。
糖尿病による蛋白尿を改善するには
腎臓の機能は一度低下すると、完全に元に戻ることはありません。しかし蛋白尿の改善により、残っている機能を保護することはできます。
方法は大きく3つあります。食事療法、運動療法、薬物療法です。ただし、何よりもまず行うべきは、病院やクリニックで専門的な検査を受けることです。
食事療法や運動療法は患者様ご自身でも実践が可能ですが、なぜ蛋白尿が出ているのか、どれだけ腎臓の機能が低下しているのかは、専門的な検査をしなければわかりません。
必要な治療も検査の結果によって変わるため、まず必要なのは検査なのです。くれぐれも自己判断で対処して、症状を悪化させることがないようご注意ください。