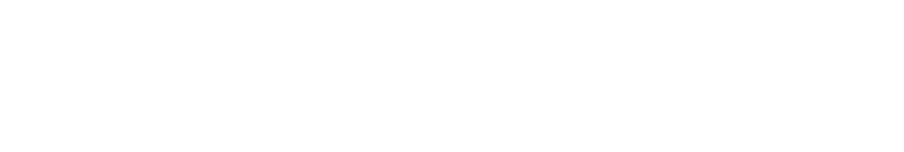- HOME>
- のどが渇く
なぜ糖尿病でのどが渇くのか

のどの渇き(口渇)は糖尿病が進行すると生じる代表的な自覚症状です。通常以上にのどが渇き、大量の水分を摂っても収まりません。
原因は血液に含まれる糖(血糖)の濃度が高くなっているからです。糖尿病は高血糖状態が続くことで、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの分泌量が減ったり、効き目が悪くなったりする疾患です。この疾患にかかると、自然と下がるはずの血糖値が下がらず、慢性的な高血糖状態になります。
糖分を多く含む液体は、粘度が高くなります。血液も同じで、血糖値の高い方の血液は健康な方の血液に比べてドロドロになります。これは人間の体にとって異常な事態なので、体は血糖値を引き下げようと、脳から「のどが渇いている」という信号を出します。水分を摂ることで血液を薄め、糖の濃度を下げようというわけです。
そのため、糖尿病が進行するとのどが渇くのです。
その他ののどの渇きが起きる疾患
しかし、運動をして汗をかいたり、空気が乾燥していたり、コーヒーやお酒などを飲んだりと、のどが乾く原因は日常生活の中にもたくさんあります。また以下で見るように、糖尿病以外にも、のどの渇きを感じる疾患はあります。
更年期障害
更年期障害とは、主に女性が閉経を迎える過程で起こる様々な身体的、精神的な変化を指します。女性ホルモンには唾液や粘膜の分泌を促進する作用がありますが、更年期障害によって女性ホルモンの分泌量が減少することで、のどの渇きを感じる場合があります。
シェーグレン症候群
シェーグレン症候群は、免疫系の異常によって唾液腺や涙腺などの分泌腺が炎症を起こし、唾液や涙の分泌量が低下する病気です。唾液の分泌が低下することで、のどが渇きを感じます。
副甲状腺機能亢進症
副甲状腺機能亢進症は、副甲状腺から分泌される副甲状腺ホルモンの過剰分泌によって引き起こされる病気です。副甲状腺ホルモンはカルシウムを排泄する作用があるため、副甲状腺機能亢進症にかかると尿の量が増加します。その結果、体内の水分量が少なくなり、のどが乾くことがあります。
尿崩症
尿崩症は、脳下垂体後葉から分泌されるホルモンの異常によって引き起こされる病気で、尿の量が過剰になることが特徴です。尿の量が過剰になることで、体内の水分が不足し、のどが渇く場合があります。
その他
その他にも、発熱やストレス性の自律神経の乱れ、薬の副作用などで、のどの渇きを感じる場合があります。
糖尿病によるのどの渇きを放置すると…
糖尿病が原因でのどの渇きを感じている場合、すでに疾患がかなり進行しているため、それ以上放置すると様々な合併症に発展する可能性がより高くなります。
糖尿病による高血糖状態が原因で血液がドロドロになると、全身の毛細血管が傷つき始めます。例えば手足の神経や網膜に通っている毛細血管、あるいは毛細血管が集まってできている糸球体(腎臓で老廃物などを濾過しているフィルター)が損傷すると、糖尿病の三大合併症と言われる糖尿病性神経障害、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症に発展します。
最悪の場合、糖尿病性神経障害は足の切断、糖尿病性網膜症は失明に繋がりますし、糖尿病性腎症は透析治療や腎臓移植が必要になります。
もしご自身に糖尿病の心当たりがある場合は、「ただのどが渇いているだけ」と考えずに、早い段階で検査と治療を受けましょう。