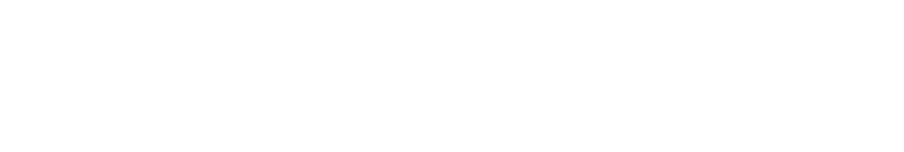- HOME>
- II型糖尿病
II型糖尿病とは
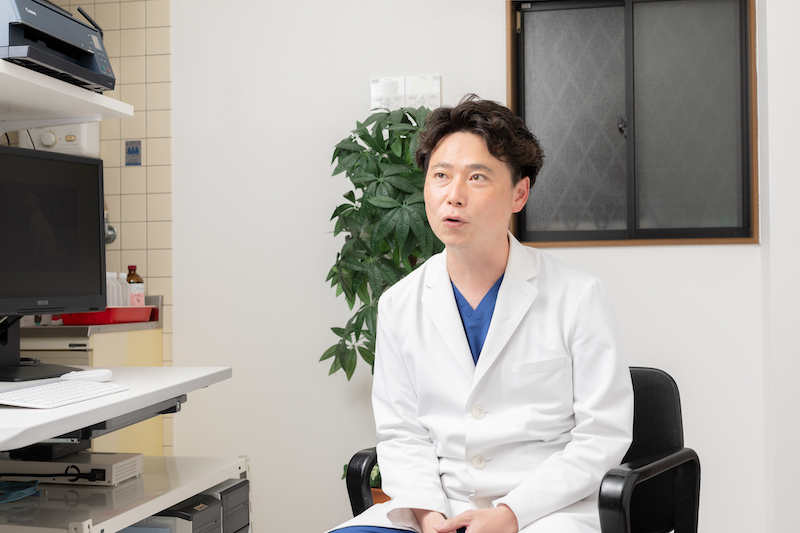
Ⅱ型糖尿病とは、インスリンの分泌やインスリンの作用が低下する疾患です。
糖は私たちの食事から抽出され、腸で吸収されます。また、食事をしない時は肝臓で糖が作られ、血液を通じて体内に運ばれます。
血液中を循環するこの糖は血糖と呼ばれ、膵臓のβ細胞から分泌されるインスリンとともに血液中を流れ、細胞内に血糖が取り込まれるサポート役を担っています。人体は糖分を主なエネルギー源として利用するため、血糖とインスリンは生命維持にとって極めて重要な役割を果たします。
Ⅱ型糖尿病になると、インスリンが十分に働かなくなるため、重症化すると血糖値が非常に高い状態が持続するようになり、多飲・多尿のほか、口が渇いたり、体重が減ったりするようになります。またそれだけでなく、命に関わるような合併症を発症するリスクが大幅に高まります。
糖尿病全体の約95%を占め、日本では40歳を過ぎてから有病率が上がり始めるほか、女性に比べて男性の方がかかりやすい傾向にあります。
II型糖尿病の原因
Ⅱ型糖尿病は、遺伝的な要因と食生活や生活習慣といった環境的な要因の組み合わせによって発症すると考えられています。
糖尿病の原因となる主な環境的な要因は、肥満、運動不足、飲酒、喫煙です。
肥満
肥満になると糖代謝、つまり体内で糖をエネルギーとして消費したり、蓄積したりする仕組みが機能不全を引き起こします。肥満状態になると、膵臓からインスリンが大量に分泌されるようになります。
この状態が長引くと、インスリンの血糖値を下げる力(血糖降下能)が低下するとともに、より多くのインスリンが分泌されるようになります。すると今度は体がインスリンに反応しにくくなり、結果として正常な血糖値を維持できなくなるのです。
運動不足
運動不足になると、本来運動によって消費されるはずの糖が血中に残ったり、脂肪に変わったりすることで、肥満の原因になります。また運動にはインスリン感受性(インスリンへの反応しやすさ)を向上させる効果がありますが、運動不足になればこれが低下する可能性もあります。
飲酒
まず、お酒に含まれるアルコールは1グラムあたり7.1キロカロリーを含むため、過度な飲酒によって肥満になる可能性があります。
また、1日あたり20~25g以上飲酒をすると、アルコールがインスリンの分泌に悪影響を及ぼし、血糖値を上昇させる可能性があると考えられています。
さらに過度な飲酒はアルコール性肝硬変やアルコール性膵炎のリスクも高めます。これらの疾患は高血糖だけでなく、重篤な低血糖の原因にもなり得ます。
喫煙
喫煙には以下の2つの作用があることから、糖尿病の原因になるとされています。
- 交感神経を刺激して血糖値を上昇させる作用
- 体内のインスリンの働きを妨げる作用
II型糖尿病の治療
Ⅱ型糖尿病の治療方法には、食事療法と運動療法、そして薬物療法の3種類があります。初期のⅡ型糖尿病は、食事療法と運動療法でコントロールすることが可能で、薬物療法を行わずに疾患と上手くお付き合いされている患者様もたくさんいらっしゃいます。
「生活習慣を変えるのは大変そう…」と思う方もいるかもしれませんが、きちんと検査をしたうえで、必要な食事や運動を見極めれば、過度な制限やトレーニングをせずとも血糖をコントロールできる場合も珍しくありません。
健康診断で糖尿病の傾向を指摘された方、薬物療法をはじめとする糖尿病治療に不安をお持ちの方は、是非一度、東大阪市・瓢箪山駅にある横内内科 循環器・糖尿病内科へご相談ください。患者様一人一人の状況に応じて、できるだけストレスの少ない、最適な治療方法をご提案いたします。